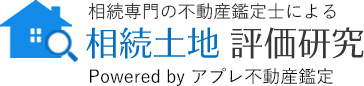- 相続土地 評価研究TOP
- その他
- 債権法(民法)改正⑤「定型約款に関する規制」
債権法(民法)改正⑤「定型約款に関する規制」

民法のなかで「債権法」などと呼ばれる、契約等に関する基本的なルールが定められている部分について、約120年ぶりに改正がありました。
(2020 年4月1日から施行)
今回は「定型約款に関する規制」について確認していきます。
約款とは
企業等が不特定多数を相手に同種の取引を定型的に行う場合に用いられる取引条項です。
インターネットサービスの利用規約や、鉄道やバスの運送約款、電気・ガスの供給約款など、不特定多数を相手に大量の取引を迅速に処理するため、あらかじめ条件を約款で定め、取引に利用します。
近年ではインターネットを利用した取引も多く、約款に基づいて契約を締結することは多々ありますが、民法には約款に関する明確な規定は記されていませんでした。
このような実情を踏まえ、改正後の民法では「定型約款」に関するルールが新設されました。
定型約款とは
約款を用いた取引で条件を満たしたものを「定型取引」とし、その定型取引で使用される約款が「定型約款」です。
【定型取引の条件】
ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの
定型約款のルール
定型約款が契約の内容であるとの合意を当事者間でするか、実際に取引を行う際に相手方に対して定型約款が契約の内容であるということを個別に表示する必要があります。
上記の条件が満たされていれば、取引の相手方が定型約款にどのような条項が含まれるのかを知らなくても合意をしたものとみなされます。
(信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項は契約の内容とはなりません)
定型約款を変更する場合のルール
長期継続する取引では、法令の変更や経済情勢等の変化に対応して、定型約款の内容に変更が必要な場合があります。
改正後の民法では、事業者が定型約款を変更するための要件についてのルールを設けました。
定型約款の変更は、以下の場合に限り認められます。
●変更が顧客の一般の利益に適合する場合
●変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
顧客にとって必ずしも利益にならない変更については、事前にインターネットなどで周知をする必要があります。
また、約款の中に事業者都合で変更する可能性について記載があっても、一方的に変更することはできません。
※執筆時点で有効